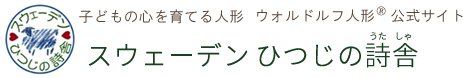- Home
- シュタイナー教育の視点から
- 「少子化について思うこと」シュタイナー教育の視点から No24
シュタイナー教育の視点から
7.132025
「少子化について思うこと」シュタイナー教育の視点から No24

出生率低下に関する報道を耳にすると、今の教育の中に抜け落ちていることがあると感じます。それは「親になる教育」です。皆さんの中で親になるための教育を受けた人はいらっしゃるでしょうか?
学校の保健体育の時間に、性教育やその延長で少しは親になることについて教わるかもしれません。しかし、親になること、子どもを育てるということについて学ぶ機会はないように思います。きっと昔は、小さな村の集団の中で、長屋のようなところで、大家族の中で、自然に伝わっていたり、教えてくれる人がいたりしたのだと思います。
今の大人たちは、自分自身の子ども時代のネガティブな経験や記憶、そして現代社会での子育てはお金もとてもかかる、保育所や学童も足りないらしいなどのネガティブな情報をたくさん受け取っていて、親になることを望まない人も増えているのではないかと思います。そして赤ちゃんを授かること、その子の成長発達に寄り添うことの素晴らしさといった、親になることや子育てをしていくことの、ポジティブな面を知るチャンスはとても少ないのです。
人間は身体だけの存在ではなく、心(魂)と精神(霊性、自我)を持つ存在で、子どもが生まれるということは、精神的な世界から地上の世界にやってくるということ。そして地上で生きて、また精神的な世界にまた帰っていくという人間観抜きに、シュタイナー教育を語ることはできません。
私はシュタイナー園の担任の時は、そのことを子どもの誕生日に、誕生日のお話として語っていました。天の国の子どもは天の国から地上に降りていく旅を始め、途中で自分のお母さんお父さんを選び、そして生まれてきて、皆が誕生を喜んだというお話です。これを聞いて育った子どもは、親しい人が亡くなったときも、天の国に帰って行ったことを、自然に感じとります。
子どもは作るものではなくて、授かるもの。このような観点があるのと無いのでは、性教育も親になる教育も全く違うものになるのだと思います。
「大きくなったら何になりたい?」という質問に対して、「お母さんになりたい!」と答える子どもはあまり見かけなくなってしまいました。お母さんお父さんに愛をもって迎えられて育った子どもは、自分が受けた愛を、自分も親になって子どもに注ぎたいと自然に考えるのではないでしょうか。家族との生活があたたかいものであり、その中でありのままの自分が受け入れられて育つ人が増えたら、少子化の傾向も変わるかもしれません。
お母さんが愛を込めて手作りしたお人形でたっぷり遊んだ子どもは、親になったら子どものためにお人形づくりを始めることでしょう。
プロフィール・吉良創 (きらはじめ)
1962年生まれ、自由学園卒。ヴァルドルフ幼稚園教員養成ゼミナール(ドイツ、ヴィッテン)修了。
滝山しおん保育園園長、南沢シュタイナー子ども園理事、日本シュタイナー幼児教育協会理事、ライアー響会代表。国内外でシュタイナー教育、ライアーに関する講座、講演、コンサート、執筆などを行っている。