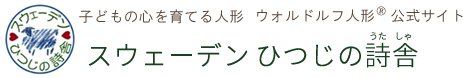- Home
- シュタイナー教育の視点から
- シュタイナー教育の視点から No25 「小人を作る」
シュタイナー教育の視点から
10.142025
シュタイナー教育の視点から No25 「小人を作る」

「小人を作る」
シュタイナー教育関連の講座で、木の小人(こびと)作りの指導をしました。ナイフ(小刀)を使い、直径3センチ長さ20センチくらいの木の枝の先を、鉛筆を削るように削っていきます。小人は5センチほどの身長ですが、枝の真ん中あたりをしっかりもって、枝の片方の先を削っていきます。削ったところは小人の尖り帽子。木の皮を髪の毛と髭の形だけ残して削り、残した髪と髭の真ん中に大きな顔の部分を丸く削ります。そして髭の下の部分で枝を鋸でまっすぐに切ります。まっすぐ切ると、小人は安定して直立します。その後全体にサンドペーパーをかけ、焼きペンで顔をつけ、透明水彩で着色した後、オイルをかけて磨きます。
子どもの前で小人を彫っていた時のこと、「なにをつくってるの?」と聞かれ「なんだろうね。」と答えていましたが、だんだん小人の姿が現れてくると、ある子どもは「あ、小人さんが枝から出てきた!」と嬉しそう。そう、枝を削っているうちにその枝の中にいた小人が出てくるのです。
子どもたちは小人が大好きで、保育室にある小人たちも愛され続けています。小人というと「根っこ小人」を思い出す人も多いと思いますが、小人(ノーム、グノーム)とは、自然界の4つのエレメント「地水火風」との関わりでは「地」の精。ホッティンガー小人をご存知の方もいらっしゃると思いますが、小人は人間の頭部(神経感覚)と似ていてプロポーションはおよそ主として頭、およそ一等身です。
地水火風との関わりでは、水の精はウンディーネ、風の精はシルフェ、火の精はサラマンダーという名前が古くからあり、昔話にも登場します。地水火風は日本の表現ですが、自然の4つのエレメントと考える場合、順番は地水風火で、火と風の順番が変わります。それぞれが自然界の物の形態、固体、液体、気体、熱とも結び付きます。そして人間の4つの気質(憂鬱質、粘液質、多血質、胆汁質)とももちろん結びついています。
手仕事をしている方で、子どもたちのために、人形劇のために、フェルトや羊毛を使って、編み物で、あるいは木を彫って小人や他の自然霊たちを作ったことのある方も多いかと思います。子どもの健やかな成長発達や人間本来の生活には自然との触れ合いはとても大切。鉱物、植物、虫や魚や鳥などの動物、山や川や海や平野、天候や季節、太陽、月、惑星や星々などなど。人間の周りの自然に興味関心を持ち、驚き、愛し、共に生きていくことがもたらすものは、とても大きいのです。
ただ、手仕事で作る小人が「かわいい」キャラクターになってしまわないように、自然の質を保った美しさを持ったものだといいと思います。私たちが手仕事で作る自然霊たちは、子どもたちの自然との関わりに、きっと何かプラスしてくれるでしょう。

プロフィール・吉良創 (きらはじめ)
1962年生まれ、自由学園卒。ヴァルドルフ幼稚園教員養成ゼミナール(ドイツ、ヴィッテン)修了。
滝山しおん保育園園長、南沢シュタイナー子ども園理事、日本シュタイナー幼児教育協会理事、ライアー響会代表。国内外でシュタイナー教育、ライアーに関する講座、講演、コンサート、執筆などを行っている。